2008年03月31日
写真の難しさ

今日は午後から雨が上がり、素晴らしい夕日が見られました。上の写真はその時のものです。
私は、趣味で山に行った時に写真を撮っていますが、なかなかこれはという写真がありません。写真を撮っていて思うのは、写真は「ピント合わせに始まってピント合わせに終わる」という感じがするなあということです。
素人にはピント合わせが難しいため、今はほとんどのカメラがオートフォーカスです。だから、ピンとなんて簡単に合うのではないの?という方もいるかと思いますが、オートフォーカスのカメラは、どこにピントを合わせてくれるのでしょうか?
人を撮せば、顔に合うカメラも出てきていますが、本当に顔にピントを合わせれば良いのでしょうか? ピントは、目に合わせるのではないですか? 目の中でもきらりと光った瞳に合わせることが重要なはずです。カメラはそこまでは合わせてくれませんし、マニュアル撮影で合わせることは、素人にはものすごく難しいことです。プロでも難しいことでしょうね。
そこまで要求しなくても、花の写真を撮る時は、オートフォーカスは全く役にたちません。ワンランク上の写真を目指す方は、まずは一眼レフデジカメを買いましょう。そして、構図など、いろんな写真撮影テクニックを学ばなければなりません。それでもそれでも写真は難しいです。
2008年03月29日
カシミールで作った絵

20代の名古屋にいた頃、北アルプスの五竜岳に行きました。
これは、自分の中でも最も思い出に残る山の一つなのですが、五竜岳に至る遠見尾根の西遠見付近にテントを張り、五竜岳のG2を登りました。そこを登ったことも大きな思い出なのですが、テント場付近から見た鹿島槍北壁は、自分にとって、最も美しい風景の一つでした。そのころ読んだ「山と渓谷」には、鹿島槍ヶ岳のことを「やさしさと厳しさを併せ持つ山」と評していましたが、まさにその通りの山だと思います。
山頂に達するだけなら、爺ヶ岳方面から行くとほとんど危険はありません。しかし、五竜岳方面の尾根からですと、キレットがあり、かなり厳しくなります。そして、北壁や天狗尾根、東尾根など、アルピニストを魅了してやまない尾根があります。
私は、結局、バリエーションルートからは行けずじまいでしたが、美しい北壁を見られたことが何よりでした。
上の絵は、カシミールで描画してみたものです。カシミールは、登山道の断面図を作ったり、とても便利なソフトです。解説本にCDがついていますので、興味をお持ちの方は、一度手に取ってみてはいかがでしょうか?
2008年03月27日
白夜の大岩壁に挑むその2
NHK取材班が出版した山野井ご夫妻の、グリーンランドでの未踏の大岩壁を登攀した様子や、お二人の出会い、普段の姿などを描いた本「白夜の大岩壁に挑む」を読んでいます。
まだ、グリーンランドの登攀の部分は、これから読むところですが、お二人の日頃のほのぼのとした様子や、クライミングからずっと離れないでいる山野井さんの様子が伝わってきて、やっぱりおすすめ本です。お二人は、山以外のことには、お金を使わず、日頃はものすごくつつましい生活をしています。そして、とても楽しそうで、ほのぼのとした感じですね。これからの登攀の様子を読むのも楽しみです。みなさんも、機会がありましたら、ぜひお読みください。
イトーヨーカドーやセブンイレブンで有名なセブンアンドアイHDは、インターネットで注文できるオンライン書店のセブンアンドワイも経営しているのですね。注文すると。近くのセブンイレブンで受け取ることができるそうです。おすすめ本が見つかるかも知れませんから、一度訪れてみてください。



まだ、グリーンランドの登攀の部分は、これから読むところですが、お二人の日頃のほのぼのとした様子や、クライミングからずっと離れないでいる山野井さんの様子が伝わってきて、やっぱりおすすめ本です。お二人は、山以外のことには、お金を使わず、日頃はものすごくつつましい生活をしています。そして、とても楽しそうで、ほのぼのとした感じですね。これからの登攀の様子を読むのも楽しみです。みなさんも、機会がありましたら、ぜひお読みください。
イトーヨーカドーやセブンイレブンで有名なセブンアンドアイHDは、インターネットで注文できるオンライン書店のセブンアンドワイも経営しているのですね。注文すると。近くのセブンイレブンで受け取ることができるそうです。おすすめ本が見つかるかも知れませんから、一度訪れてみてください。

2008年03月26日
ほんの少し役にたった知識
今年に入ってアスペルガーのことを、何冊かの本を読んで勉強しました。そこで得たわずかばかりの知識をある方に話していました。そしたら、その方が東北の実家に帰った時、子どもがアスペルガーだという知り合いの方がいたそうです。
その子は、小学生時代からいじめられていたそうで、今は高校生なのですが、やはりいじめにあい、今は学校を辞めてしまったそうです。
東北の田舎のため、まだアスペルガーの知識を持った先生がほとんどいなくて、対応ができていなかったようです。親も、今回の話でようやく分かったそうです。私が話した方は、アスペルガーに関する本を買って、知り合いの方に送るそうです。アスペルガー症候群とは何かということが分かると、対応は大きく違ってくるはずです。
アスペルガーの子どもは、端から見ると、親のしつけが悪いとしか見えないのです。親も、しつけが悪いと思われたくないので、間違ったことをすると、一所懸命に叱ります。これが、ますますアスペルガーの子どもを追いつめていきます。
アスペルガーの子どもは、叱っても全く身に付きません。それよりも、何で叱られたのかが分からず、パニックになり、叱った相手に悪い感情が積み上がっていくだけです。
叱るのではなく、なぜそうすることが良くないことなのか根気よく教えていくことが大切なのだと思います。アスペルガーの子どもは頭が悪くないため、理詰めで反論してくるかも知れませんが、大人の側はそれに対してもできる限り理論で伝えることが必要だと思います。まあ、面倒くさくなるだろうけど、あきらめないことですね。
アスペルガーの子どもは、社会的ヒエラルキー(暗黙の上下関係)や暗黙のルールが理解できません。これは、大人になっても理解できないままの場合が多いように思います。自分より年上の人に恥をかかせていても、何でもなかったように、その後その人と付き合おうとするようですし、自分が問題を起こしても、人から強く注意されたりしなければ、何もなかったようにけろりという感じです。自分が相手や周囲の人からどう思われているかということは、全く感じないようです。大人になってからは、周囲の人もどう接して良いか難しい面がありますね。言っても分かってもらえないし、何か言えば、自分の理屈で逆にこちらを責めてくるし、どのように接したらよいのでしょうか? これからの課題です。
その子は、小学生時代からいじめられていたそうで、今は高校生なのですが、やはりいじめにあい、今は学校を辞めてしまったそうです。
東北の田舎のため、まだアスペルガーの知識を持った先生がほとんどいなくて、対応ができていなかったようです。親も、今回の話でようやく分かったそうです。私が話した方は、アスペルガーに関する本を買って、知り合いの方に送るそうです。アスペルガー症候群とは何かということが分かると、対応は大きく違ってくるはずです。
アスペルガーの子どもは、端から見ると、親のしつけが悪いとしか見えないのです。親も、しつけが悪いと思われたくないので、間違ったことをすると、一所懸命に叱ります。これが、ますますアスペルガーの子どもを追いつめていきます。
アスペルガーの子どもは、叱っても全く身に付きません。それよりも、何で叱られたのかが分からず、パニックになり、叱った相手に悪い感情が積み上がっていくだけです。
叱るのではなく、なぜそうすることが良くないことなのか根気よく教えていくことが大切なのだと思います。アスペルガーの子どもは頭が悪くないため、理詰めで反論してくるかも知れませんが、大人の側はそれに対してもできる限り理論で伝えることが必要だと思います。まあ、面倒くさくなるだろうけど、あきらめないことですね。
アスペルガーの子どもは、社会的ヒエラルキー(暗黙の上下関係)や暗黙のルールが理解できません。これは、大人になっても理解できないままの場合が多いように思います。自分より年上の人に恥をかかせていても、何でもなかったように、その後その人と付き合おうとするようですし、自分が問題を起こしても、人から強く注意されたりしなければ、何もなかったようにけろりという感じです。自分が相手や周囲の人からどう思われているかということは、全く感じないようです。大人になってからは、周囲の人もどう接して良いか難しい面がありますね。言っても分かってもらえないし、何か言えば、自分の理屈で逆にこちらを責めてくるし、どのように接したらよいのでしょうか? これからの課題です。
2008年03月24日
ミツマタ
 昨日は、丹沢にあるミツバ岳という山に行ってきました。
昨日は、丹沢にあるミツバ岳という山に行ってきました。ここは、山の所有者が山頂に植えたそうですが、立派なミツマタが咲き誇っていました。とにかく、こんなに立派にたくさんのミツマタが咲いているところははじめてみました。素晴らしいの一言で、低山ですが来て良かったと思える山です。ただし、これから木々が葉を付けると、全く展望がなくなりそうです。山頂の一画から富士山は見られると思いますが。どちらかというと尾根の一画という感じです。
とにかくミツマタが見事で、一見の価値ありです。機会があったら行ってみてください。ただし、山頂からの下りで道を外れて分からなくなり、警察に連絡した方がいたようですので、注意は必要です。地図に登山道も書かれていません。

2008年03月20日
雨の一日
今日は、雨になってしまい、少し時間ができました。壊れてしまったFAXを買いに行きたいと思います。
 雨の日は、山に行かず、家にいることが多いのですが、雨の日も山や自然はいろんなものを見せてくれます。写真は、一昨年の夏、栗駒山で撮影したウラジロヨウラクの花と水滴です。水滴は、どうして?と思うほど、反り返った萼にもきれいに付いています。萼や茎の表面にあるわずかな毛に付いているのでしょう。自然は、こんなに美しいものを誰に見せるためでもなく、ただそこにあるだけなんですね。自分もここまで無心の境地になれたら素晴らしいなと思うのですが・・・・・。
雨の日は、山に行かず、家にいることが多いのですが、雨の日も山や自然はいろんなものを見せてくれます。写真は、一昨年の夏、栗駒山で撮影したウラジロヨウラクの花と水滴です。水滴は、どうして?と思うほど、反り返った萼にもきれいに付いています。萼や茎の表面にあるわずかな毛に付いているのでしょう。自然は、こんなに美しいものを誰に見せるためでもなく、ただそこにあるだけなんですね。自分もここまで無心の境地になれたら素晴らしいなと思うのですが・・・・・。
「ひきこもりの若者と生きる」に、著者の方が、引きこもる若者たちの多くが、なぜ人を怖がるのか?という疑問をこれから考えていきたいと書いていました。競争社会に確かに多くの問題が潜んでいるのですが、決してそれだけではないはずです。私自身も、会社に入ったばかりの頃は、対人恐怖の傾向がありました。なぜそうなったかというと、子どもの頃からいろんな年代の人たちと付き合ってこなかったために、自分を出せなかったし、どうやって付き合ったらよいかということも分からなかったからです。やはり経験がなかったということが一番大きかったように感じます。
経験がなかったということだけが原因とは思いませんが、今の子どもたちは、私以上に、親や学校の管理下に置かれ、「あれをしてはダメ、こうしなければダメ」と、親が道筋を立て、それからはみ出ることを許してもらえない状況にあると思います。失敗や親から見てやってはいけないことも、子どもは経験して、いろんなことを自然に学んでいくのだろうと思うのですが、それができないことが、人との接し方も分からなくしてしまうのかも知れません。全てではないにしても、原因の一つではないかと思います。
 雨の日は、山に行かず、家にいることが多いのですが、雨の日も山や自然はいろんなものを見せてくれます。写真は、一昨年の夏、栗駒山で撮影したウラジロヨウラクの花と水滴です。水滴は、どうして?と思うほど、反り返った萼にもきれいに付いています。萼や茎の表面にあるわずかな毛に付いているのでしょう。自然は、こんなに美しいものを誰に見せるためでもなく、ただそこにあるだけなんですね。自分もここまで無心の境地になれたら素晴らしいなと思うのですが・・・・・。
雨の日は、山に行かず、家にいることが多いのですが、雨の日も山や自然はいろんなものを見せてくれます。写真は、一昨年の夏、栗駒山で撮影したウラジロヨウラクの花と水滴です。水滴は、どうして?と思うほど、反り返った萼にもきれいに付いています。萼や茎の表面にあるわずかな毛に付いているのでしょう。自然は、こんなに美しいものを誰に見せるためでもなく、ただそこにあるだけなんですね。自分もここまで無心の境地になれたら素晴らしいなと思うのですが・・・・・。「ひきこもりの若者と生きる」に、著者の方が、引きこもる若者たちの多くが、なぜ人を怖がるのか?という疑問をこれから考えていきたいと書いていました。競争社会に確かに多くの問題が潜んでいるのですが、決してそれだけではないはずです。私自身も、会社に入ったばかりの頃は、対人恐怖の傾向がありました。なぜそうなったかというと、子どもの頃からいろんな年代の人たちと付き合ってこなかったために、自分を出せなかったし、どうやって付き合ったらよいかということも分からなかったからです。やはり経験がなかったということが一番大きかったように感じます。
経験がなかったということだけが原因とは思いませんが、今の子どもたちは、私以上に、親や学校の管理下に置かれ、「あれをしてはダメ、こうしなければダメ」と、親が道筋を立て、それからはみ出ることを許してもらえない状況にあると思います。失敗や親から見てやってはいけないことも、子どもは経験して、いろんなことを自然に学んでいくのだろうと思うのですが、それができないことが、人との接し方も分からなくしてしまうのかも知れません。全てではないにしても、原因の一つではないかと思います。
2008年03月19日
原田知世のちょっとモニタになってミル?
いつもアンケートに答えているマクロミルのページにある、「原田知世のちょっとモニタになってミル?」を見てみました。インターネットの市場調査に答えて、自分が普段思っていることが商品開発に生かされたら素晴らしいと思いますが、私にはちょっと無理そうです。原田知世さんだからこそかも知れません。座談会形式のモニタもありますが、私はまだ参加したことがありません。「原田知世のちょっとモニタになってミル?」のビデオは、アンケートに参加する方法や回答によってもらえるポイントなどを分かりやすく説明しています。一度、見てみてください。
私は、もう数年、マクロミルのモニタに参加していますが、日用品を買ったりすることがほとんどないので、あまり効果的な回答をできずにいるように感じています。ただ、先日、我が家の女房がマクロミルに参加したのですが、事前アンケートで絞り込まれてからの本アンケートがバシバシ来ていて、もうポイントは私を追い抜いたのではないでしょうか? まあ、私はぼちぼちマイペースで答えて、わずかな小遣い稼ぎになればよいかな程度で、気軽に時間のある時に回答しています。
「原田知世のちょっとモニタになってミル?」はコチラから!
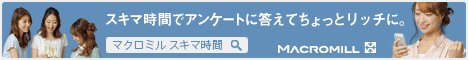
私は、もう数年、マクロミルのモニタに参加していますが、日用品を買ったりすることがほとんどないので、あまり効果的な回答をできずにいるように感じています。ただ、先日、我が家の女房がマクロミルに参加したのですが、事前アンケートで絞り込まれてからの本アンケートがバシバシ来ていて、もうポイントは私を追い抜いたのではないでしょうか? まあ、私はぼちぼちマイペースで答えて、わずかな小遣い稼ぎになればよいかな程度で、気軽に時間のある時に回答しています。
「原田知世のちょっとモニタになってミル?」はコチラから!
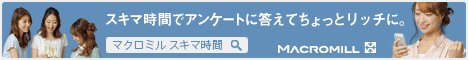
2008年03月17日
ひきこもりの若者と生きる
「ひきこもりの若者と生きる」という本を、ほぼ読み終わりました。
この本を読んで、若者たちの自立を支援するビバハウスや、それを取り巻く支援してくれるみなさんの心に打たれました。本当に、若者たちのために、頭と心と体をふるに使って働いている様子が良く分かりました。
この本の中に、書かれていた、引きこもりの若者たちが幸せな人たちを見ると、みんな落ち込んでしまったという場面がありました。(少し前に触れていますが) ここを読み、さらに考えてみて、引きこもる若者たちの多くに共通していると思えるのは、「落ちこぼれ感」なのではないかなと思いました。以前、思ったのは、失敗を恐れることが引きこもりの大きな原因になっていると思っていました。ですが、それが最大の原因ではないなとも思っていたのですが、一番大きな原因は、「落ちこぼれ感」のように感じました。
あるがままの自分を認めるというのは、かなり難しいことだと思います。世の中には、「他の人は関係ない、自分はこうだ」という人もいますが、まじめな人ほど、自分が劣っている部分に目がいってしまうんですね。でも、これは「常に上昇、成長し続けなければならない」という価値観に支配されている面もあるように思います。高度成長期に生まれ育ってきた人は、親の世代が「欧米に追いつけ追い越せ」の精神で、裕福になり、それが成功の証でしたから、「成長指向こそが人間の生き方だ」という価値観を持っているのでしょう。子どもたちは、それに縛られて、付いていけないことで、苦しんでいるのかも知れません。これらのことを考えると、引きこもりやニートは、決して本人や親だけの問題ではなく、社会全体の問題なんだと思います。
こんなふうに書くと、簡単に結論に達したように見えますが、社会全体の問題をどのようにとらえるのか、どのように細分化していくのか、どのように良くしていくのか、答えはなかなか出ません。というより、これはという答えは見つかる訳はないのです。
私は、障害の有無や年齢に関わらず「共に楽しむ」ことが大切なことであり、「共に生きる」につながることだと思っています。単なる登山ですが、なぜ共に楽しむことができるのか、どうしたら共に楽しむことができるのか、楽しんでいるように見えて本当に楽しんでいるのだろうか、などなど共に楽しむということだけを取り上げても、答えなどない無限の深さがあるのですね。にぎやかに話している時、誰かが「話をしている場合じゃないだろう」と怒鳴ったら、それで楽しさは吹っ飛びます。そうならないようにどうしたらよいのか、安全を第一にして、楽しさを追求する。簡単なようで、すごく難しいことですね。「共に楽しむ」という一つのことを考えただけで、無限の深さがあるのですから、生きるということは無限の深さを持っているということですね。結論を求める気持ちを持ちながら、とにかく行動を続けることが必要です。
この本を読んで、若者たちの自立を支援するビバハウスや、それを取り巻く支援してくれるみなさんの心に打たれました。本当に、若者たちのために、頭と心と体をふるに使って働いている様子が良く分かりました。
この本の中に、書かれていた、引きこもりの若者たちが幸せな人たちを見ると、みんな落ち込んでしまったという場面がありました。(少し前に触れていますが) ここを読み、さらに考えてみて、引きこもる若者たちの多くに共通していると思えるのは、「落ちこぼれ感」なのではないかなと思いました。以前、思ったのは、失敗を恐れることが引きこもりの大きな原因になっていると思っていました。ですが、それが最大の原因ではないなとも思っていたのですが、一番大きな原因は、「落ちこぼれ感」のように感じました。
あるがままの自分を認めるというのは、かなり難しいことだと思います。世の中には、「他の人は関係ない、自分はこうだ」という人もいますが、まじめな人ほど、自分が劣っている部分に目がいってしまうんですね。でも、これは「常に上昇、成長し続けなければならない」という価値観に支配されている面もあるように思います。高度成長期に生まれ育ってきた人は、親の世代が「欧米に追いつけ追い越せ」の精神で、裕福になり、それが成功の証でしたから、「成長指向こそが人間の生き方だ」という価値観を持っているのでしょう。子どもたちは、それに縛られて、付いていけないことで、苦しんでいるのかも知れません。これらのことを考えると、引きこもりやニートは、決して本人や親だけの問題ではなく、社会全体の問題なんだと思います。
こんなふうに書くと、簡単に結論に達したように見えますが、社会全体の問題をどのようにとらえるのか、どのように細分化していくのか、どのように良くしていくのか、答えはなかなか出ません。というより、これはという答えは見つかる訳はないのです。
私は、障害の有無や年齢に関わらず「共に楽しむ」ことが大切なことであり、「共に生きる」につながることだと思っています。単なる登山ですが、なぜ共に楽しむことができるのか、どうしたら共に楽しむことができるのか、楽しんでいるように見えて本当に楽しんでいるのだろうか、などなど共に楽しむということだけを取り上げても、答えなどない無限の深さがあるのですね。にぎやかに話している時、誰かが「話をしている場合じゃないだろう」と怒鳴ったら、それで楽しさは吹っ飛びます。そうならないようにどうしたらよいのか、安全を第一にして、楽しさを追求する。簡単なようで、すごく難しいことですね。「共に楽しむ」という一つのことを考えただけで、無限の深さがあるのですから、生きるということは無限の深さを持っているということですね。結論を求める気持ちを持ちながら、とにかく行動を続けることが必要です。
2008年03月15日
春山
春爛漫になってきましたが、山は底雪崩のシーズンを迎えます。しかし、その前に少しの間、雪の状態が安定する時期があります。今年は、急に暖かくなったため、どうなのか分かりませんが、3月中旬は、北アルプスの鹿島槍ヶ岳などの北壁も登られています。
 以前、セピア色の頃ですが、遠見尾根にテントを張って、五竜岳のG2に登ったことがありました。その日は無風快晴に恵まれて、最高の登山日和でした。写真は、日の出の後、テントと五竜岳を撮したものです。人里から遠く離れた尾根の上に、4泊しました。顔はもう真っ黒、山頂からの剣岳も素晴らしかったですし、テント場からの鹿島槍北壁は、自分の生涯の中で出会った最も美しい風景でした。またいつか、3月の遠見尾根に行ってみたいですね。
以前、セピア色の頃ですが、遠見尾根にテントを張って、五竜岳のG2に登ったことがありました。その日は無風快晴に恵まれて、最高の登山日和でした。写真は、日の出の後、テントと五竜岳を撮したものです。人里から遠く離れた尾根の上に、4泊しました。顔はもう真っ黒、山頂からの剣岳も素晴らしかったですし、テント場からの鹿島槍北壁は、自分の生涯の中で出会った最も美しい風景でした。またいつか、3月の遠見尾根に行ってみたいですね。
 以前、セピア色の頃ですが、遠見尾根にテントを張って、五竜岳のG2に登ったことがありました。その日は無風快晴に恵まれて、最高の登山日和でした。写真は、日の出の後、テントと五竜岳を撮したものです。人里から遠く離れた尾根の上に、4泊しました。顔はもう真っ黒、山頂からの剣岳も素晴らしかったですし、テント場からの鹿島槍北壁は、自分の生涯の中で出会った最も美しい風景でした。またいつか、3月の遠見尾根に行ってみたいですね。
以前、セピア色の頃ですが、遠見尾根にテントを張って、五竜岳のG2に登ったことがありました。その日は無風快晴に恵まれて、最高の登山日和でした。写真は、日の出の後、テントと五竜岳を撮したものです。人里から遠く離れた尾根の上に、4泊しました。顔はもう真っ黒、山頂からの剣岳も素晴らしかったですし、テント場からの鹿島槍北壁は、自分の生涯の中で出会った最も美しい風景でした。またいつか、3月の遠見尾根に行ってみたいですね。2008年03月14日
障害とは何でしょうか?
障害とは何でしょうか?
障害者という文字の中に含まれる「害」という字が害虫と同じ意味だということで、障碍者とか障がい者という言い方が、少しずつ広がってきているように思います。
しかし、そのように言葉を問題視している人たちのうち、どれだけの方が「障害とは何か」というような自問をしてしているでしょうか? 私には、疑問に感じます。
「障害者」という言葉や定義は、障害者基本法で定義されているとおり、法律で定めた障害を持つ人です。ですから、中には、障害者として認定して欲しくても、認定してもらえない人たちもいます。難病の人たちの中には、まさにそれで苦しんでいる方もいるそうです。
私自身は、言葉については、法律での使用が変わったら、それに従おうと思いますが、それよりももっと深いところを考えたいと思っています。
表現がかなり難しいところで、誤解を受けやすいのですが、「自然は決して無駄なものを作らない」といわれます。私自身、山の自然にいつも触れていますが、まさにその通りだと実感しています。そして、最も身近な自然は、自分自身の身体であり、人の身体です。これは、まさに自然が作りだしたものです。だとすると、障害も自然が作りだしたもののはずです。障害とは何か、障害というものをどのように受け止めたらよいのか、これを追求するのは人間に課せられた一つの大きな課題だと思います。
先日、立教大学のある学生さんが、全盲のご主人と健常者の奥さんを見て、ご主人の苦労と共に、奥さんの苦労も相当なものがあったのだろうと、これまでのことを推し量っていました。
私は、障害とは、障害を持った人だけのものではなくて、障害を持つ人と関わる人にとっても、大きな問題を提起してくれているのだと思っています。障害を持つ人も、持たない人も、障害というものを通して、それが持つ意味や意義、なぜ障害があるのかなどを考えることこそ、生涯学習ではないかと思います。カルチャースクールで、既存の知識を詰め込むことが生涯学習ではありません。実践を通して、自らの頭で考え抜くことです。(子どもたちにも、そのことを教えていきたいと思っていますが)
以前、視覚障害者のガイドヘルパーの資格を取るために、講習を受けたことがあるのですが、その時、全盲の方が講師でしたが、こう言っていました。「目が見えていた時と見えなくなってからを比較すると、見えなくなってからの方が、圧倒的に人間関係の幅が広がった」と。視覚障害者の人たちの中には、「俺は目さえ見えていれば、人の世話になどならなくて良いのだ」という方がいます。そう思う方の気持ちも十分に分かる面もあるのですが、人の世話になる、人との関わりが増えるということを、どのように受け止めるかで、その人の人生に対する姿勢が大きく変わってくるように思います。難しいかも知れませんが、人との関わりが増えたこと、人の世話になれたことを、うれしいと思えた時、きっと幸せな気持ちが湧いてくるのではないでしょうか? 私も、いつどんな障害を持つかは分かりません。でも、どんな障害を持っても、幸せになりたいと思っています。「幸福」とは、自分が幸福だと思えば幸福になります。幸福だと思えること、うれしいなと思えることを、たくさんたくさん見つけていきたいですね。
以前、ある中学生にこんな話をしたことがあります。「人には、どうして大きいとか小さいとか、頭がよいとか悪いとか、いろんな差があるのか知っているかい?」と聞いたのですが、その子は、思った通り、分からないと言っていました。私はその子に、「人と差があることで、劣等感を持ったり、優越感を持ったりするだろう。そういう気持ちを持つことが大切なことだから、神様は差を付けたんだよ。だって、自分自身が劣等感を持ったことがなければ、劣等感で苦しむ人の気持ちは分からないだろう。だからね、劣等感を持つということは、すごく大切なことなんだよ。優越感も同じさ。神様は、そのことを考えて欲しくて、差を付けているんじゃないだろうか?」と話しました。劣等感を持った子どもに、「あなたには、いくつも良いところがあるのだから、そんなことで悩まなくて良いよ」と言う優しい親御さんは多いと思います。ですが、自分の長所を褒めてもらえたことはうれしいけど、悩まなくて良いと言われている劣等感を持ってしまう自分は、やっぱりダメな人間なんだと思ってしまうのではないでしょうか? 「悩まなくても良い」と言われても、現実に悩む自分がいるのだし、「悩まなくても良い」という言葉自体が、悩んでいる今の子どもを否定していると思うのです。そうではなくて、劣等感を持ったこと自体を、高く評価することが大切だと思います。子どもが劣等感を持ったら、赤飯を炊いてお祝いするくらいでも良いかも知れませんよ。だって、劣等感を持った経験のない子どもは、劣等感を持つ人の気持ちが分からないのだから。人の心の痛みを感じることのできる人間に成長する大切なステップを上がっているところなのではないかと思います。そんな素晴らしい経験をしているのです。
神様は、決して無駄なものを作らないはずです。それを無駄だと思うか、大切なことだと思うかは、全てはその人にかかっているはずですね。
ただ、確かに、障害は不便です。その不便さを受け入れる気持ちに本人自身が切り替えることと、不便さを少しでも解消する社会の支援は欠かせませんが。
障害者という文字の中に含まれる「害」という字が害虫と同じ意味だということで、障碍者とか障がい者という言い方が、少しずつ広がってきているように思います。
しかし、そのように言葉を問題視している人たちのうち、どれだけの方が「障害とは何か」というような自問をしてしているでしょうか? 私には、疑問に感じます。
「障害者」という言葉や定義は、障害者基本法で定義されているとおり、法律で定めた障害を持つ人です。ですから、中には、障害者として認定して欲しくても、認定してもらえない人たちもいます。難病の人たちの中には、まさにそれで苦しんでいる方もいるそうです。
私自身は、言葉については、法律での使用が変わったら、それに従おうと思いますが、それよりももっと深いところを考えたいと思っています。
表現がかなり難しいところで、誤解を受けやすいのですが、「自然は決して無駄なものを作らない」といわれます。私自身、山の自然にいつも触れていますが、まさにその通りだと実感しています。そして、最も身近な自然は、自分自身の身体であり、人の身体です。これは、まさに自然が作りだしたものです。だとすると、障害も自然が作りだしたもののはずです。障害とは何か、障害というものをどのように受け止めたらよいのか、これを追求するのは人間に課せられた一つの大きな課題だと思います。
先日、立教大学のある学生さんが、全盲のご主人と健常者の奥さんを見て、ご主人の苦労と共に、奥さんの苦労も相当なものがあったのだろうと、これまでのことを推し量っていました。
私は、障害とは、障害を持った人だけのものではなくて、障害を持つ人と関わる人にとっても、大きな問題を提起してくれているのだと思っています。障害を持つ人も、持たない人も、障害というものを通して、それが持つ意味や意義、なぜ障害があるのかなどを考えることこそ、生涯学習ではないかと思います。カルチャースクールで、既存の知識を詰め込むことが生涯学習ではありません。実践を通して、自らの頭で考え抜くことです。(子どもたちにも、そのことを教えていきたいと思っていますが)
以前、視覚障害者のガイドヘルパーの資格を取るために、講習を受けたことがあるのですが、その時、全盲の方が講師でしたが、こう言っていました。「目が見えていた時と見えなくなってからを比較すると、見えなくなってからの方が、圧倒的に人間関係の幅が広がった」と。視覚障害者の人たちの中には、「俺は目さえ見えていれば、人の世話になどならなくて良いのだ」という方がいます。そう思う方の気持ちも十分に分かる面もあるのですが、人の世話になる、人との関わりが増えるということを、どのように受け止めるかで、その人の人生に対する姿勢が大きく変わってくるように思います。難しいかも知れませんが、人との関わりが増えたこと、人の世話になれたことを、うれしいと思えた時、きっと幸せな気持ちが湧いてくるのではないでしょうか? 私も、いつどんな障害を持つかは分かりません。でも、どんな障害を持っても、幸せになりたいと思っています。「幸福」とは、自分が幸福だと思えば幸福になります。幸福だと思えること、うれしいなと思えることを、たくさんたくさん見つけていきたいですね。
以前、ある中学生にこんな話をしたことがあります。「人には、どうして大きいとか小さいとか、頭がよいとか悪いとか、いろんな差があるのか知っているかい?」と聞いたのですが、その子は、思った通り、分からないと言っていました。私はその子に、「人と差があることで、劣等感を持ったり、優越感を持ったりするだろう。そういう気持ちを持つことが大切なことだから、神様は差を付けたんだよ。だって、自分自身が劣等感を持ったことがなければ、劣等感で苦しむ人の気持ちは分からないだろう。だからね、劣等感を持つということは、すごく大切なことなんだよ。優越感も同じさ。神様は、そのことを考えて欲しくて、差を付けているんじゃないだろうか?」と話しました。劣等感を持った子どもに、「あなたには、いくつも良いところがあるのだから、そんなことで悩まなくて良いよ」と言う優しい親御さんは多いと思います。ですが、自分の長所を褒めてもらえたことはうれしいけど、悩まなくて良いと言われている劣等感を持ってしまう自分は、やっぱりダメな人間なんだと思ってしまうのではないでしょうか? 「悩まなくても良い」と言われても、現実に悩む自分がいるのだし、「悩まなくても良い」という言葉自体が、悩んでいる今の子どもを否定していると思うのです。そうではなくて、劣等感を持ったこと自体を、高く評価することが大切だと思います。子どもが劣等感を持ったら、赤飯を炊いてお祝いするくらいでも良いかも知れませんよ。だって、劣等感を持った経験のない子どもは、劣等感を持つ人の気持ちが分からないのだから。人の心の痛みを感じることのできる人間に成長する大切なステップを上がっているところなのではないかと思います。そんな素晴らしい経験をしているのです。
神様は、決して無駄なものを作らないはずです。それを無駄だと思うか、大切なことだと思うかは、全てはその人にかかっているはずですね。
ただ、確かに、障害は不便です。その不便さを受け入れる気持ちに本人自身が切り替えることと、不便さを少しでも解消する社会の支援は欠かせませんが。
2008年03月12日
白夜の大岩壁に挑む
昨年放送された「白夜の大岩壁に挑む」が、NHK取材班が執筆した単行本として出版されたのですね。私もまだ読んでいないので、読んでみようと思っています。
山野井泰史さん、妙子さん夫妻が、未登のグリーンランドの大岩壁を登った記録です。
テレビで見ると、クラックを利用した内面登攀を中心として登っていましたが、比べることもできませんが、昔登った東尋坊の柱状節理のクラックが少しあんな感じだったなと思い出しました。わずか20m程でしたが、滑りやすく、自殺の名所のため、「奈落」という名前が付いていました。
 その時の写真がないので、御在所の藤内壁、一の壁フランケの宇宙遊泳を登った時の写真を掲載しました。この部分は広いクラックですが、以外と簡単で、5.9位です。難しいのは左上にあるクラックで、5.10bくらいでした。まだ、フリークライミングが流行りだしたばかりだったため、同じ御在所には、ウサギの耳という岩場に、ウェイクアップというルートがありました。今まで人口登攀(ハーケンやボルトを使い、それにアブミなどをかけて登る方法)で登られていたルートを、フリーで登りはじめたころでした。
その時の写真がないので、御在所の藤内壁、一の壁フランケの宇宙遊泳を登った時の写真を掲載しました。この部分は広いクラックですが、以外と簡単で、5.9位です。難しいのは左上にあるクラックで、5.10bくらいでした。まだ、フリークライミングが流行りだしたばかりだったため、同じ御在所には、ウサギの耳という岩場に、ウェイクアップというルートがありました。今まで人口登攀(ハーケンやボルトを使い、それにアブミなどをかけて登る方法)で登られていたルートを、フリーで登りはじめたころでした。
さすがに、昔のようには登れませんが、4級くらいまでなら登れると思っているのですが、どうかな~?
山野井泰史さん、妙子さん夫妻が、未登のグリーンランドの大岩壁を登った記録です。
テレビで見ると、クラックを利用した内面登攀を中心として登っていましたが、比べることもできませんが、昔登った東尋坊の柱状節理のクラックが少しあんな感じだったなと思い出しました。わずか20m程でしたが、滑りやすく、自殺の名所のため、「奈落」という名前が付いていました。
 その時の写真がないので、御在所の藤内壁、一の壁フランケの宇宙遊泳を登った時の写真を掲載しました。この部分は広いクラックですが、以外と簡単で、5.9位です。難しいのは左上にあるクラックで、5.10bくらいでした。まだ、フリークライミングが流行りだしたばかりだったため、同じ御在所には、ウサギの耳という岩場に、ウェイクアップというルートがありました。今まで人口登攀(ハーケンやボルトを使い、それにアブミなどをかけて登る方法)で登られていたルートを、フリーで登りはじめたころでした。
その時の写真がないので、御在所の藤内壁、一の壁フランケの宇宙遊泳を登った時の写真を掲載しました。この部分は広いクラックですが、以外と簡単で、5.9位です。難しいのは左上にあるクラックで、5.10bくらいでした。まだ、フリークライミングが流行りだしたばかりだったため、同じ御在所には、ウサギの耳という岩場に、ウェイクアップというルートがありました。今まで人口登攀(ハーケンやボルトを使い、それにアブミなどをかけて登る方法)で登られていたルートを、フリーで登りはじめたころでした。さすがに、昔のようには登れませんが、4級くらいまでなら登れると思っているのですが、どうかな~?
2008年03月11日
引きこもる若者
今、「ひきこもりの若者と生きる」という本を読んでいます。
この本は、北海道の余市で引きこもりの若者たちと一緒に暮らしながら支援しているビバハウスを開設し、運営している安達さんご夫妻が書いた、ビバハウスの7年の歩みです。
まだ、読んでいる途中ですが、この本の中で、若者たちは、春、みんながこれから何かやろうという輝きに満ちたような時期が、一番落ち込むのだそうです。
どこかの水族館に行って、アベックを見たり、幸せそうな幼子を連れた家族を見て、みんなが落ち込んでしまったという話も出ていました。
そんな時、彼らになっていったらよいのか私も良く分からないのですが、少なくても、一見幸せそうに見える人たちも、決して幸せではない場合もあるし、上辺だけを繕っている場合もあります。仲の良い恋人同士だと思ったら、デートバイオレンスで、暴力をふるっている人もいるでしょう。私には、そんな人たちよりも、引きこもっていたとしても、自分の生き方などに、真剣に向き合って考えている若者の方が、ずっと将来性もあるし、信頼できるのではないかと思います。だから、もっと自信を持って生きて良いと思うんですよね。
この本は、北海道の余市で引きこもりの若者たちと一緒に暮らしながら支援しているビバハウスを開設し、運営している安達さんご夫妻が書いた、ビバハウスの7年の歩みです。
まだ、読んでいる途中ですが、この本の中で、若者たちは、春、みんながこれから何かやろうという輝きに満ちたような時期が、一番落ち込むのだそうです。
どこかの水族館に行って、アベックを見たり、幸せそうな幼子を連れた家族を見て、みんなが落ち込んでしまったという話も出ていました。
そんな時、彼らになっていったらよいのか私も良く分からないのですが、少なくても、一見幸せそうに見える人たちも、決して幸せではない場合もあるし、上辺だけを繕っている場合もあります。仲の良い恋人同士だと思ったら、デートバイオレンスで、暴力をふるっている人もいるでしょう。私には、そんな人たちよりも、引きこもっていたとしても、自分の生き方などに、真剣に向き合って考えている若者の方が、ずっと将来性もあるし、信頼できるのではないかと思います。だから、もっと自信を持って生きて良いと思うんですよね。
2008年03月10日
四阿屋山に行ってきました

昨日は、「学びあい、支えあい」地域活性化推進事業の活動で、秩父の四阿屋山に行って来ました。四阿屋山と書いて、「あずまやさん」と読みます。知っていましたか?
この山は、セツブンソウとフクジュソウで有名な山です。上の写真は、セツブンソウです。とにかく小さくて可憐な花です。右の写真は、山居で初めて見たフクジュソウの仲間の秩父紅という花だそうです。

フクジュソウやロウバイ、紅梅が、きれいに咲いていました。山中にある山居は、ロウバイの良い香りでいっぱいでした。山仲間アルプのサイトに多くの写真が掲載されていますので、ぜひご覧ください。
2008年03月07日
太宰治に思う
私の好きな作家の1人に、超暗いな~と思われるかも知れませんが、太宰治がいます。
もううろ覚えになってしまっているため、もしかしたら間違っている箇所があるかも知れませんが、その時はご容赦お願いします。
もう10年以上前になるでしょうか? ある視覚障害者の人が、「人間失格」に、「生きていてすみません」と書かれていたけど、すごい皮肉だねと言っていました。私は、太宰治のことをある程度知っていたので、生い立ちや彼の考え方を説明し、分かってもらいました。
太宰治は、当時の大地主、庄屋の息子として生まれました。小作農から米を巻き上げ、それで豊かな暮らしをしていたのですが、太宰治は、そういう自分の立場が、許し難いものと感じていたそうなのです。そういう立場にいる自分は、生きている資格のない醜い人間だと、自らを卑下していたそうです。そのため、自殺未遂を繰り返し、4回目に玉川上水に身を投げて亡くなったのです。それは、40歳を目前にした日だったそうです。本の解説には、人としてのあるべき姿から外れる自分を追いつめてきたが、そういう純粋さを追求できるのも40歳が限度と感じていたのではないかと書かれていたように記憶しています。
今日、太宰治のことを考えていて、ふと思ったのですが、代表作の「走れメロス」の中で、自分の行く道を氾濫した川が遮り、友を見捨てようとする場面を描いていましたが、あれは太宰治自身が自分自身の人生の中で感じたことだったのではないかと感じました。
小作農をいじめる自分の一族を否定し続けていたものの、どこかで「こんなことにこだわらず、庄屋として優雅に暮らした方が自分にとって得策ではないのか」という気持ちが湧き上がってきた時があったのではないかと感じました。
「人間失格」の中で、3葉の写真をあげ、醜い人間が写っていると言っていますが、当然、あの写真は自分自身だと思います。自分に都合良く上手く立ち回ろうとしている自分がいることを取り上げていると思いますが、この部分で、「走れメロス」につながるように感じます。
「人間失格」の冒頭部分に、写真に醜い子どもが写っていることや、それを取り巻く形だけ取り繕う人たちが集まっていることが書かれていますが、太宰治は、このように表面だけを取り繕って、うまく立ち居振る舞いをする人間模様に、ものすごい嫌悪感を持っていたのではないかと思います。
正直言って、私もそんな人たちに囲まれていたら、やっていられないっす。本音で話すことのできる仲間がいることが、何よりも大切なことではないかと思います。本音で話せる時、心がすごく軽くなるように思うからです。
しばらくぶりで太宰治を読んでみたくなりました。
もううろ覚えになってしまっているため、もしかしたら間違っている箇所があるかも知れませんが、その時はご容赦お願いします。
もう10年以上前になるでしょうか? ある視覚障害者の人が、「人間失格」に、「生きていてすみません」と書かれていたけど、すごい皮肉だねと言っていました。私は、太宰治のことをある程度知っていたので、生い立ちや彼の考え方を説明し、分かってもらいました。
太宰治は、当時の大地主、庄屋の息子として生まれました。小作農から米を巻き上げ、それで豊かな暮らしをしていたのですが、太宰治は、そういう自分の立場が、許し難いものと感じていたそうなのです。そういう立場にいる自分は、生きている資格のない醜い人間だと、自らを卑下していたそうです。そのため、自殺未遂を繰り返し、4回目に玉川上水に身を投げて亡くなったのです。それは、40歳を目前にした日だったそうです。本の解説には、人としてのあるべき姿から外れる自分を追いつめてきたが、そういう純粋さを追求できるのも40歳が限度と感じていたのではないかと書かれていたように記憶しています。
今日、太宰治のことを考えていて、ふと思ったのですが、代表作の「走れメロス」の中で、自分の行く道を氾濫した川が遮り、友を見捨てようとする場面を描いていましたが、あれは太宰治自身が自分自身の人生の中で感じたことだったのではないかと感じました。
小作農をいじめる自分の一族を否定し続けていたものの、どこかで「こんなことにこだわらず、庄屋として優雅に暮らした方が自分にとって得策ではないのか」という気持ちが湧き上がってきた時があったのではないかと感じました。
「人間失格」の中で、3葉の写真をあげ、醜い人間が写っていると言っていますが、当然、あの写真は自分自身だと思います。自分に都合良く上手く立ち回ろうとしている自分がいることを取り上げていると思いますが、この部分で、「走れメロス」につながるように感じます。
「人間失格」の冒頭部分に、写真に醜い子どもが写っていることや、それを取り巻く形だけ取り繕う人たちが集まっていることが書かれていますが、太宰治は、このように表面だけを取り繕って、うまく立ち居振る舞いをする人間模様に、ものすごい嫌悪感を持っていたのではないかと思います。
正直言って、私もそんな人たちに囲まれていたら、やっていられないっす。本音で話すことのできる仲間がいることが、何よりも大切なことではないかと思います。本音で話せる時、心がすごく軽くなるように思うからです。
しばらくぶりで太宰治を読んでみたくなりました。
2008年03月06日
アスペルガー症候群
アスペルガー症候群という本を読んでみました。
アスペルガーは、高機能自閉症ともいわれていて、自閉症の一種で、程度がかなり軽い方という感じのようです。一般的な自閉症の人は、自分だけの世界を生きているのですが、アスペルガーの人は、みんなの世界の中で自分1人で生きているという感覚なのだそうです。
そのため、相手の気持ちになって考えることができず、場を読むとか暗黙の了解という概念が分からないそうです。社会的なヒエラルキーが分からず、目上の人を目上と思わないため、平気でバカ呼ばわりしたりできるようですね。形式張った話し方や細かい点にこだわった話し方になりやすく、言葉を字義通りに受け取りやすい面もあるそうです。
アスペルガーの人には、とにかくひとつひとつ、論理的に教えてあげることが必要なようです。「こうしてはいけない」という否定的な言い方ではなく、「こういう場合には、こうだから、こうした方が良いんだよ」と教える必要があるようです。
アスペルガーの人は、100人に1人くらいいるという統計もあるようで、以外と近いところにいるかも知れませんね。アスペルガーの特徴を良く掴んで対処するようにしないと、すぐに衝突して喧嘩になってしまいそうです。
アスペルガーの本は、かなりたくさん出ているようです。アマゾンで「アスペルガー症候群」で検索したら、70冊以上ヒットしました。アスペルガーだけなら、もっとヒットしそうです。一度読んでみてはいかがでしょうか?
アスペルガーは、高機能自閉症ともいわれていて、自閉症の一種で、程度がかなり軽い方という感じのようです。一般的な自閉症の人は、自分だけの世界を生きているのですが、アスペルガーの人は、みんなの世界の中で自分1人で生きているという感覚なのだそうです。
そのため、相手の気持ちになって考えることができず、場を読むとか暗黙の了解という概念が分からないそうです。社会的なヒエラルキーが分からず、目上の人を目上と思わないため、平気でバカ呼ばわりしたりできるようですね。形式張った話し方や細かい点にこだわった話し方になりやすく、言葉を字義通りに受け取りやすい面もあるそうです。
アスペルガーの人には、とにかくひとつひとつ、論理的に教えてあげることが必要なようです。「こうしてはいけない」という否定的な言い方ではなく、「こういう場合には、こうだから、こうした方が良いんだよ」と教える必要があるようです。
アスペルガーの人は、100人に1人くらいいるという統計もあるようで、以外と近いところにいるかも知れませんね。アスペルガーの特徴を良く掴んで対処するようにしないと、すぐに衝突して喧嘩になってしまいそうです。
アスペルガーの本は、かなりたくさん出ているようです。アマゾンで「アスペルガー症候群」で検索したら、70冊以上ヒットしました。アスペルガーだけなら、もっとヒットしそうです。一度読んでみてはいかがでしょうか?
2008年03月02日
失われた50年
今日は、八千代市の市民活動サポートセンター主催の「NPOフォーラムinやちよ」にスタッフとして行ってきました。
このフォーラムで心に残ったのは、ある方が言ったこれまでの50年はあまりにも異常な期間だったということです。私も、確かにその通りだと思いました。
とにかく、「欧米に追いつけ追い越せ、競争に負けるな、お金を稼いで物質的に豊かになれ」という価値観がほとんどの人を支配していたように思います。そんな社会の流れが、子どもたちにも大きく影響し、良い大学に入るために効率よく勉強しろ。勉強をするためなら、家のことなど手伝わなくても良い。大学に上げるためなら、お金をどんどん稼ぐ。
そんな社会の中で、大人になった子どもは、人との接し方も困難の乗り越え方も分からず、引きこもることになります。親から価値観を押しつけられて、そのストレスをいじめという形で表してしまいます。いろんな禁止事項を作っても、企業は消費者のわがままに答えることが業績の向上につながるため、子どもには悪いといわれるテレビゲームもどんどん作ります。また、投資家は、どんな形でも儲かっている会社に投資します。
そんな世知辛い社会の中で、隣近所の人間関係は希薄になり、コミュニティが薄れてきました。暑ければエアコンをがんがん使います。公共の乗り物よりも自動車が便利ですから、1人でも乗り回して、温暖化ガスをたくさん排出しています。
いろんな問題点の犯人は、決して1人ではありません。誰が悪いということではなく、みんなが犯人です。これまでの50年は一体何だったのか、失われた50年と言っても良いのではないでしょうか?
そして、大切なのはこれからの50年、100年をどういう方向に進めていくべきなのかですね。誰かが決めてくれるんじゃなくて、自分が決めていかなければならない。自分のという人間の経営者は自分です。自分という人間は、自分が思ったとおりの人間にしかなりません。だから、少しでも良くなる方向に向けて、進んでいきたいなと思います。
このフォーラムで心に残ったのは、ある方が言ったこれまでの50年はあまりにも異常な期間だったということです。私も、確かにその通りだと思いました。
とにかく、「欧米に追いつけ追い越せ、競争に負けるな、お金を稼いで物質的に豊かになれ」という価値観がほとんどの人を支配していたように思います。そんな社会の流れが、子どもたちにも大きく影響し、良い大学に入るために効率よく勉強しろ。勉強をするためなら、家のことなど手伝わなくても良い。大学に上げるためなら、お金をどんどん稼ぐ。
そんな社会の中で、大人になった子どもは、人との接し方も困難の乗り越え方も分からず、引きこもることになります。親から価値観を押しつけられて、そのストレスをいじめという形で表してしまいます。いろんな禁止事項を作っても、企業は消費者のわがままに答えることが業績の向上につながるため、子どもには悪いといわれるテレビゲームもどんどん作ります。また、投資家は、どんな形でも儲かっている会社に投資します。
そんな世知辛い社会の中で、隣近所の人間関係は希薄になり、コミュニティが薄れてきました。暑ければエアコンをがんがん使います。公共の乗り物よりも自動車が便利ですから、1人でも乗り回して、温暖化ガスをたくさん排出しています。
いろんな問題点の犯人は、決して1人ではありません。誰が悪いということではなく、みんなが犯人です。これまでの50年は一体何だったのか、失われた50年と言っても良いのではないでしょうか?
そして、大切なのはこれからの50年、100年をどういう方向に進めていくべきなのかですね。誰かが決めてくれるんじゃなくて、自分が決めていかなければならない。自分のという人間の経営者は自分です。自分という人間は、自分が思ったとおりの人間にしかなりません。だから、少しでも良くなる方向に向けて、進んでいきたいなと思います。



















